読めて、書けて、受かる中学受験専門国語塾。
TEL 052-918-2779
営業時間:14:50-22:10
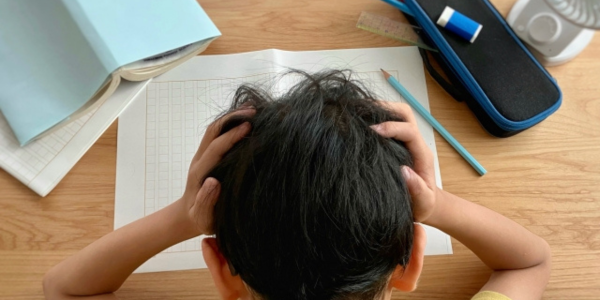
1.ワンセンテンス・ワンテーマ(これを常に意識して書くこと)
→ひとつの文にあれもこれも書きたいことを詰め込むと意味不明の文になる。
2.短い文を接続詞で繋げてある文章は読み手にとって理解しやすい。
例1)~である。したがって、~である。
例2)~である。しかし、~ではないであろうか。
3.以下のような接続助詞は原則として使うべきではない。
例1)~であるので~である。
例2)~であるが~ではないであろうか。
4.長くなりそうなら、いったん句点で区切り、接続語を使って次の文と繋げるといい。
→古文が読みにくいのは一文がだらだらと途切れず長く続くから。国語の記述問題でそれをやってはいけない。
5.無駄な言葉はなるべく削る。
→強調語は削っても意味はとおる。そして実は削った方が文は締まる。
例1)非常に美しい→美しい すこぶる強い→強い とても優しい→優しい
例2)とても、非常に、すこぶる、等々は削っても構わない強調語である。
6.原則として、ひとつの文に主語はひとつ、述語はひとつ。
→そうでないと変な文章になる。書いた文章を貫く論理がねじれかねない。言い換えると論理的整合性が崩れてしまう(←こうなるとアウト)。
7.なるべく下書きをする。
→自分で文章を書いて、それを自分の眼で確かめることで、はじめて自分が何を考えているか判る。これは最近、亡くなった詩人の谷川俊太郎さんも述べていた。
→下書きは汚くていい。自分だけが分かればいいので読み手に気を遣わなくても大丈夫。記号、絵など何でもアリ。
8.文の終わりに気をつける。
例1)なぜか、と理由を尋ねられたら、「~だから。」「~なので。」で締めくくる。
例2)どういうことか説明しなさい、という設問には「~こと。」で締めくくる。
9.自分の書いた文章を他の人に見てもらう。
→他の人におかしな点はないか見てもらおう。自分では気づかない点を指摘してもらえるはずだ。きっと新しい発見があるはず。岡目八目という言葉もあるではないか。
10.最初から上手く書けるわけがない。
→だからこそ今から対策をする意味がある。最初は悪戦苦闘するかも知れない。しかし、それは皆、同じである。一度目よりも二度目、二度目よりも三度目の方が上手く行く(自分の経験から)。
スペースの関係上ここには書くことができなかった様々な方法やコツが、まだまだたくさんあります。最もいいのはお子さまに当塾の授業を受けていただくことです。是非ご検討ください。

コメント